「おろしあ」とは江戸時代におけるロシアの呼び名だが、「おふらんす」とは言葉の重みが違う。「ロシア」を巻き舌で発音すると「ォロシア」と聞こえるが、これが正しい発音かどうかは知らない。
『おろしあ国酔夢譚』をお読みになったことがあるだろうか。井上靖の名作である。今日は、その主人公、大黒屋光太夫の故郷をレポートする。天気がよいので、気持ちのいい旅が出来そうだ。
鈴鹿市若松西四丁目の伊勢若松駅前に、「大黒屋光太夫之像」がある。スタンリーやリヴィングストンといった西洋の探検家かと見まがうが、ロシア帰りの日本人である。
光太夫は地域の誇りである。遥かに遠いロシアから故郷に凱旋したかのようなイメージだ。胸にはエカテリーナ2世からいただいた金メダルが輝いている。説明板を読んでみよう。
大黒屋光太夫は、宝暦元年(一七五一)伊勢国南若松村(現在の鈴鹿市若松東)に生まれ、天明二年(一七八二)に遠州灘にて遭難、翌年ロシアに漂着、十年後の寛政四年(一七九二)に帰国した。その見聞体験は『北槎聞略』という書物に残されており、文政十一年(一八二八)七八歳で江戸にて没した。本像は、鈴鹿市出身の稲垣克次氏の制作である。
『北槎聞略(ほくさぶんりゃく)』は、蘭学者の桂川甫周が光太夫から聞いたことをまとめたロシア地誌である。その波瀾万丈の漂流譚は、井上靖の手で小説となり、緒方拳主演の映画となって人口に膾炙した。私はみなもと太郎『風雲児たち』で知った。
光太夫の統率力は船員の命を救い、その記憶力は蘭学の発展に寄与し、人生そのものが作家の創作意欲を掻き立てた。『おろしあ国酔夢譚』執筆にあたって、井上靖は『北槎聞略』を基本資料としたが、連載中の昭和41年3月、若松にも取材に訪れている。
鈴鹿市若松中一丁目の若松小学校にも「大黒屋光太夫之像」がある。
こちらは座って何か書いている。光太夫は帰国後の寛政六年(1794)に大槻玄沢が主催した「おらんだ正月」に招かれた。この様子を描いた『芝蘭堂新元会図』(大槻玄沢関係資料、国重文)で、光太夫はロシア語を書いて見せているが、像はこれをモデルにしているらしい。像の建立は昭和42年。当時、『おろしあ国酔夢譚』の連載で、光太夫はちょっとしたブームになっていた。
ちなみに駅前の像は、昭和62年に若松小学校創立百周年を記念して制作され、もとは小学校にあった。光太夫の人生は、まさに学校教育が目指す「生きる力」のお手本なのだ。
鈴鹿市若松中二丁目に「大黒屋光太夫顕彰碑」がある。
この碑は三代目である。初代は大正7年に建てられたが、昭和9年の室戸台風で破損した。二代目は千代崎海岸に建てられたが、昭和34年の伊勢湾台風の被害を受けた。三代目は昭和51年に建てられた。
「開国曙光」の篆額は、貴族院議長正二位勲一等公爵徳川家達によるものだ。光太夫を我が国の国際化の先駆者として顕彰している。撰文は『広辞苑』で有名な新村出博士である。文中に次のような一節がある。
彼地に在りて欽定世界辞典の修訂に与かりたるは亦奇遇とすべし
この「欽定世界辞典」というのは、ペーター・ジーモン・パラス編『欽定全世界言語比較辞典』のことで、ロシア語と世界各地の言語を比較した辞典である。その中の日本語の部分を、当時サンクト・ペテルブルグに滞在していた光太夫が校閲したのであった。さすがは言語学者の新村博士、目の付け所がちがう。
光太夫の波瀾万丈伝は、千代崎漁港の若松緑地の壁画で知ることができる。光太夫一行17名が乗った神昌丸は、紀州藩の廻米を江戸に運ぶため、白子湊を出帆した。天明二年(1782)12月9日のことである。しかし14日、遠州灘で暴風に遭い、船は漂流してゆくこととなる。上の絵は、その時の様子である。
鈴鹿市若松東一丁目に「大黒屋光太夫供養碑」がある。鈴鹿市指定の史跡である。
この供養碑には、天明四年(1784)12月の年月が刻まれているが、この時、光太夫一行は流れ流されアリューシャン列島のアムチトカ島で生きていた。供養碑が建てられたのは、消息不明の光太夫一行が全員遭難死したものと思われたからである。
一行17名のうち、1名は神昌丸船上で、11名がロシア国内で死んだ。2名は正教に改宗してロシアに残り、日本に帰還したのは光太夫と小市、磯吉の3名であった。石碑正面に「光太夫」、側面に「小市」と磯吉(碑では「豊松」)の名が刻まれている。
光太夫ら3名は、1792年10月20日(寛政4年9月5日)、遣日使節ラクスマンのエカテリーナ号で根室に到着した。上の写真はエカテリーナ号を模した遊具で、若松緑地にある。
その後、光太夫は文政11年(1828)に亡くなるまで江戸に住んだ。ただ、一度だけだが若松に帰郷している。享和二年(1802)のことである。おそらく自らの供養碑も目にしただろう。遭難から約20年間の出来事が、次から次へと脳裏に去来したに違いない。
「すべては酔って眠った間の夢だったか」 そう、酔夢譚だったのである。

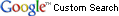
コメント