季節の移ろいに私たちは詩情を喚起させられるが、初春に生きる喜びは格別だ。萌えいづる春の中で、思い切り背伸びをしたくなる。この時季に決まって思い起こすのは川端康成『古都』の冒頭である。春のやさしさとの出会い、それは一期一会、今でしか感ずることのできない抱擁感である。
やさしい春は長続きしない。だからこそ人はそれを惜しみ、その感情を詩歌に表そうとするのであろう。本日は春を惜しむ気持ちを見事に表現した文学碑を紹介する。
岡山県和気郡和気町藤野の和気神社に「近松秋江(ちかまつしゅうこう)文学碑」がある。
神社に参拝する人は多い。この文学碑に関心を抱く人はどのくらいいるのだろう。台石が苔むし古びて見えるが、その碑文は時代を越えて私たちの心に響く。読んでみよう。
彼岸桜がもう三四分どほりは花を開いてゐる。桜は梅とちがつて花を開きかけると瞬くまに開いてしまふ。それがなんだか春を享楽するに心が追はれてゐるやうである。
『都会と田園』(人文社、大正12)所収「早春」の一節である。今しかないんだと思った多くの人は写真に記録するだろう。才能のある人は詩歌に詠むだろう。秋江は随筆として表現した。ならば秋江は随筆家なのか。文学碑の傍らに木製の説明板があり、三十数年の時を経てずいぶん傷んでいる。
明治九年、当時の藤野村に生まれ、本名を徳田浩司といい、ペンネームは近松門左衛門と秋の絵を好んだことからといわれる。
県立岡山中学(現・朝日高校)を中退後、上京・帰京を繰り返し、そのころから文学、特に樋口一葉の作品に感動して作家を志したといわれる。
明治三十一年、東京専門学校(現・早稲田大学)に入学、同郷の正宗白鳥と親交する。
卒業後、時評や文学者論を雑誌・新聞に寄稿。明治四十三年「別れたる妻に送る手紙」を発表して文壇にデビュー。その後、「執着」「疑念」、大正十一年には名作「黒髪」「狂乱」「霜凍る宵」等を次々に発表した。これら一連の作品は、わが国独特の私小説というジャンルを成立させたといわれている。
晩年は目を患い、不遇な生活を送り、昭和十九年、六十八才で死去した。
昭和五十九年三月 和気町
私小説というジャンルのパイオニアである。文中の作品タイトルだけでも、どこかドロドロとしたものが感じられよう。しかし、秋江は叙情豊かな随筆も多く残している。文学碑に刻まれた一節は、京都祇園の八坂の塔あたりの情景である。エッセイストとしての評価があってもよいのではないか。
三月も下旬となり、例年に比べて早く桜が咲き始めた。今年も花見は自粛気味だが、春宵一刻値千金。今しかない季節を楽しみながら食事をすれば、総務官僚の7万円会食に劣らぬ贅沢を味わうことができるだろう。

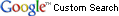
コメント