反英闘争というと英領植民地での出来事のようだが、今日は幕末日本の話である。アフリカであれ日本であれ、反英闘争とは、イギリスの帝国主義的圧力に対するその国のナショナリズムの発露である。
港区高輪三丁目の東禅寺は「最初のイギリス公使宿館跡」である。昨年2月に国の史跡に指定された。
安政6年(1859)6月に、英国総領事(11月から公使)ラザフォード・オールコックの宿所として提供され、慶応元年(1865)6月までの7年間、英国公使館として使用された。その当時からは改築が進んだものの奥書院と玄関が旧時のままだそうだ。
玄関の柱の傷がある。この寺はイギリス公使館となったが故に二度も襲撃を受け、東禅寺事件としてその名が日本史に刻まれている。これはその時の刀痕かもしれないそうだ。
第一次東禅寺事件は文久元年(1861)5月28日、14名の水戸浪士がイギリス公使ラザフォード・オールコックを狙って襲撃したものだ。襲撃の趣意書には「神州夷狄の為に相汚され候を傍観致候に忍びず」とある。
第二次東禅寺事件は文久2年(1862)5月29日、伊藤軍兵衛という松本藩士の襲撃によりイギリス人2名が殺害されたものである。
オールコックの『大君の都』(岩波文庫・下)には、第一次事件の模様が次のように描かれている。
たしかにその夜は、わたしは危険のことなどすこしも考えずに横になった。いつも召し使いがわたしの化粧台の上に置いておく習慣になっていた連発ピストルのはいった二つの箱も閉めたままで、そのひとつはカギがかかったままになっていたほどだ。いつもは不意に備えて、まくらの下に連発ピストルを置いてねるのがわたしの習慣だったのである。わたしが疲れてぐっすりねむっていたところへ、ひとりの若い通訳見習い生がやってきた。かれに与えられた仕事は、毎晩最後に主として火事の予防のために邸内を一巡し、召し使いが寝につき、火を消してあるかどうかをたしかめることであった。この見習いが暗いちょうちんをもってわたしの寝台のそばにきてわたしを起こし、公使館が襲撃され暴徒〔水戸の浪士一四名〕が門内に押し入っていると報告した。わたしは起きあがったが半信半疑であった。護衛の者が馬小屋の世話をする別当(ベットー)〔馬丁〕がばくちでもやっているか、それとも酔っぱらってけんかでもしているのだろうとわたしは信じた。だが箱から連発ピストルをとり出し、その場にゆこうとして入り口の方へ五歩も歩かないうちに、突然オリファント氏が血まみれになって現われた。腕にぱっくり開いた傷口と首の傷から血が流れていた。と思うまもなく、こんどは長崎駐在領事のモリソン氏が、やられたと叫びながら現われた。ひたいの刀傷から血が流れていた。もちろんわたしは、かれらを襲った連中が追跡してくるものと思い、発砲して阻止する身構えをしてしばらくじっとしていた。その間に負傷した人びとは奥のわたしの寝室にはいっていった。このときに武装していたのは、わたしだけだった。モリソン氏はまだ弾丸を三発あましていたが、傷のために目が見えず気がとおくなっていた。
驚いたことにだれも追ってこなかった。わたしの周囲に集まってきた人びとのうちのひとりが、わたしのもう一方の箱を開けてピストルをとり出したが、他の二人はなにももっていなかった。オリファント氏は、最初の警報を耳にするや、いそいでテーブルの上の狩猟用の重いむちをとり、自分の部屋から通じている廊下で、襲撃してくる男たちにそのむちだけで立ち向かったのである。実際、まず護衛の者が、そして家をとり巻く一五〇名の連中〔護衛〕は、だれひとりとしてわれわれを助けにやってこようとはしなかったのだ。
オリファント氏の出血がひどかったので、わたしはピストルを置いて、わたしのハンカチでかれの腕の傷をしばらねばならなかった。こうしているあいだに、つぎの部屋でひとしきり物を打つ音がした。徒党のうちの何人かが明らかに恐ろしい物音をたてて、庭に面しているガラス戸から押し入っていたのだった。しかるに役人(ヤコニン)や護衛はだれひとりとしてこの音に気がつかぬようであった。
このころまでには二連発のライフルに装填し終わっていたが、その場に居合わせたのはひとりの召し使いをいれて、われわれ五名のヨーロッパ人だけで武器は十分ではなかった。あとの二名は手傷を負っていたから、ただの一瞬たりともこの人たちを暗殺者たちの猛威にさらしておくわけにはゆかなかった。いったい敵は何人なのか、われわれには推測できなかったし、またどの方面からわれわれに襲いかかってくるか皆目見当がつかなかった。敵は多勢にせよ無勢にせよ、たっぷり10分間ほどのあいだは邸内はまったくかれらにじゅうりんされるがままであった。どうなっているかわからない不安のために、この時間がそれ以上に長く感じられたのはむりもない。かれらが部屋へ押し入ろうとしているのか、出ようとしているのかさっぱりわからなかった。そしてまた、いつ何時かれらが、かれらのいる部屋につづいている戸外の通路を通ってわれわれのいる部屋へなだれこんでくるか、あるいはかれらが破壊している場所から一ヤード以内のところにある地面に近い窓からはいってくるかわかったものではなかった。こうしているあいだにわたしは、直接にかれらのいる方角に面している窓から、至近弾をいっせいに浴びせかけてはどうかということを考えたりもした。しかし、われわれは少数だったし、かれらの方は押しこんできてわれわれの抵抗を打ち負かすほど大勢かも知れなかった。とはいえ、かれらはきっとわたしの部屋へやってくる道がわからなかったのであろう。かれらが時間を浪費すればするほど、われわれにとっては貴重なもうけものとなった。われわれの生命をゆだねられている護衛の者が裏切りでもしないかぎりは、まったくわれわれを見捨ててしまうなどということは考えられなかったからである。どこから敵が攻め込んでくるのかはっきりわからぬことが恐ろしく、それにたとえすこしのあいだたりともオリファント氏を床の上に、かばう者もないままに放って置きたくないという気持ちの方が強くて、結局のところわたしは、そこにとどまって成り行きを待とうと決心した。物音がやんだ。助けがやってきたのか、すくなくとも外部になにか変わった事態が生じて、襲撃者たちが他の方向に向かったのか、または退却したのではないか、というふうに考えられた。そのときになってやっとわたしは、負傷者をのこして二名の者といっしょに建て物のはずれにいるもうひとりの館員〔マクドナルド〕をさがしにいった。かれが姿を見せなかったので、変事が起こっているのかもしれないからだ。わたしは行く途中で、通訳見習い生のひとりであるローダー氏を入り口から通じている長い通路と他の二方面からの通路を見渡せるかどに見張りにのこしておいた。それから一〇歩も行かぬうちに、突然かれのピストルの音がしたので引き返してみると、武装した一団が通路のはずれに姿を見せていた。誰何に応じないので、かれは当然のことながら、彼らのまん中に発砲したのだった。通路で射ったのだから、ねらいがはずれるはずはなかったにちがいない。とにかくかれらはいそいで退却してしまった。われわれが襲撃者の姿を目撃したのは、これが最後だった。
水戸浪士側は首領格の有賀半弥ら3名がその場で死亡。他の浪士も切腹したり捕縛されたりした。中には坂下門外の変や天誅組の変に参加した者もいたようだ。墓碑銘によると有賀半弥は明治44年に正五位を追贈されている。愛国心とテロル、現代も解決していない重い課題である。

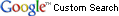
コメント