和歌には、枕詞(まくらことば)、掛詞(かけことば)、縁語、序詞、歌枕、本歌取りなど、さまざまな表現の技がある。たったの31文字が、その字数にとどまらない空間的な広がり、心情的な深まりを見せるのは、これらの修辞のおかげだ。
百人一首の中でもとりわけ秀歌と言われる97番「来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ」は、序詞、掛詞、縁語、歌枕、本歌取りと、幾重にも技巧が駆使されている。さすがは藤原定家、自薦の最高傑作である。
奈良県生駒郡斑鳩町神南四丁目の三室山の頂上に「能因法師供養塔」がある。平安中期の人物だ。
これは供養塔であって墓ではない。墓は高槻市古曽部町三丁目の「伝能因法師墳」だそうだ。三室山に供養塔が建てられたのは、あの有名な歌があるからだろう。
三室山の登り口に歌碑がある。在原業平の「千早ふる」の歌のレポートでも紹介した。
嵐吹く三室の山の もみぢ葉は 竜田の川の錦なりけり
能因法師
嵐が吹き、三室山のもみじの葉が竜田川に散って、まるで錦の帯のようだよ。百人一首69番だが、決して技巧的な歌ではない。読んだまんまである。だからと言って能因法師の作歌能力を疑ってはならない。勅撰入集六十数首を誇る歌詠みなのである。
面白いのは、鎌倉時代の『古今著聞集』巻第五「和歌第六」に記された次のエピソードだ。
能因は、いたれるすきものにてありければ、
都をばかすみとともに立ちしかどあきかぜぞふく白河の関
とよめるを都にありながらこの歌を出ださん事念なしと思ひて、人にもしらせず、久しく籠(こも)り居て、色をくろく日にあたりなして後、陸奥国の方へ修行の次(ついで)によみたりとて、披露し侍(はべ)りける。
能因法師は大変ものずきな人だ。「都を春に出発したのに、白河の関に着いたら秋になっちゃったよ」という歌は、実際には東北地方に行かずに、都にいたままで作ったという。白河の関は有名な歌枕だから、実際に行ってないのに歌に詠み込むことは多い。
能因法師が「すきもの」なのは、これでは芸がないと思い、人に見つからないようずっと家にいて、日に当たって身体を焼いてから、「みちのくひとり旅で詠みましてね」と言って披露したことだ。
偽装工作と言えば聞こえが悪いが、行ったこともない歌枕を平気で歌に詠んでいた当時にあっては、逆にリアリティを追求した努力の人と評価できよう。
こんな面白い人は、江戸川柳の格好のネタとなる。
能因はすでに霍乱(かくらん)するところ
「あー、しんど…」能因法師が倒れそうになってます。さあ法師、早く家の中へ。日に当たり過ぎて、もう少しで(=すでに)日射病(=霍乱)になるところでした。
松島を聞けば能因口ごもり
「ほぉ、みちのくでっか。ほなら、松島はどないでした?」「☆$※▼…」行ってないんだから、聞かれても答えられません。どうする?能因法師…。
わらじくい迄(まで)は能因気がつかず
「よう歩きはったのに、おみ足がきれいでんな」するどいツッコミが入りました。長く歩くと、「わらじくい」といって、わらじの緒で足の皮がむけちゃうんですね。日焼けはしていても、歩いた様子がない。危うし、能因法師…。
小栗清吾『江戸川柳おもしろ偉人伝一〇〇』(平凡社新書)を読むと、後世の人が好き勝手に想像して面白い話をつくっていることが分かる。まあ、実在の能因法師も、こんな親しみやすい人柄だったのだろう。少なくとも藤原定家のようなとっつきにくさはなかったと思われる。

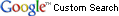
コメント