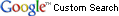瀬戸大橋は遠きにありて思ふもの、近きに寄りて眺むるもの、渡るものにはあるまじや。開通してしばらくは往復1万円かかり、渡るのにはかなりの覚悟を要した。海上に橋を架けるという人類の偉業は橋の上を走るよりも、たもとから見上げるほうがよく分かると、ここをよく訪れたものだ。
倉敷市下津井田之浦(たのうら)一丁目の田土浦(たづちのうら)公園に「平行盛歌碑」がある。この広い敷地は大橋建設当時、本州側作業地として利用されていた。
田土浦は田之浦の古い呼び名だそうだ。極めて現代的な大型インフラと平家公達の儚い栄華というアンバランスも面白い。倉敷市の水島地区も高度成長を支えたコンビナートと源平の水島合戦の二つの顔がある。
そして謡曲の題材となった藤戸合戦ゆかりの地もたくさんある。つまり倉敷市の魅力は美観地区であり、児島ジーンズであり、源平合戦なのである。合戦の経過については副碑に詳しく記されているので読んでみよう。
水島合戦
木曽義仲の軍が京都を平定した勢いで水島まで攻め寄せたが、海戦の経験のない木曽源氏は大敗した。
下津井合戦
平家物語の六ヶ度の軍(いくさ)によると、平教盛とその子の通盛、教経が下津井に在陣していた時、阿波、讃岐の兵どもが源氏に寝返って、兵船十餘艘で下津井に攻め寄せたが、教経に一喝されて退去した。万葉歌人平賀元義は、この合戦を次のように歌った。
教経が怒りし時の顔思へば波さへ騒ぐ下津井の海
一の谷合戦
元暦元年(一一八四年)二月、この戦いに平家完敗し、経盛、忠度、通盛、知章、教盛らが戦死し、将兵も半ばを亡う。
藤戸合戦の前夜
元暦元年の秋を迎えると、源軍三万の蹄の音が屋島の平家に届いてくる。藤戸合戦の総大将平行盛は、源氏を児島で迎え撃つために下津井田之浦に進駐した。玉葉和歌集巻第十七によると、備前壇之浦で八月十五日夜行盛とともに仲秋の月を愛でた全性法師が
ひとりのみ浪間にやどる月を見て昔の友や面かげにたつ
と詠んだ。
平行盛は
もろともにみし世の人は波の上に面影うかぶ月ぞ悲しき
と返した。壇之浦とは、ここ下津井田之浦である。行盛は過ぎし日の平氏の盛時を想い、仲秋の名月をともに眺めた。今は亡き歌友の面影を偲ぶこの歌からは無常と死と没落の吐息が洩れてくる。
倉敷市を舞台とした水島、下津井、藤戸の合戦が時系列に整理されていて分かりやすい。本日紹介している下津井合戦は、『平家物語』巻第九「六箇度軍」で語られている。読んでみよう。時は寿永三年(1184)の初め頃である。
平家福原へ渡(わたり)給ひて後は、四国の兵ども随(したが)ひ奉らず。中にも阿波讃岐の在庁(ざいちやう)ども、平家を背(そむ)いて源氏に付(つか)むとしけるが、「抑(そもそも)我等は昨日今日まで、平家に随(したが)うたるものの、今日始めて源氏の方へ参りたりとも、よも用ゐられじ。いざや平家に矢一つ射懸(いかけ)て、其を面(おもて)にして参らん」とて、門脇中納言、子息越前三位、能登守父子三人、備前国下津井にましますと聞えしかば討ちたてまつらんとて、兵船十余艘で寄せたりける。能登守是を聞き、「悪(にく)い奴原(やつばら)かな。昨日今日迄、我等が馬の草切(きッ)たる奴原が、既に契りを変ずるにこそ有(あん)なれ。其儀ならば、一人も洩(もら)さず討てや。」とて、小舟共に取乗て、「余すな、漏すな。」とて攻め給へば、四国の兵共、人目ばかりに矢一つ射て、退(のか)んとこそ思ひけるに、手痛う攻られ奉て、叶はじとや思ひけん、遠負(とほまけ)にして引退き、都の方へ逃上るが、淡路国福良(ふくら)の泊に著にけり。
清盛の異母弟門脇中納言教盛とその子、越前三位通盛、そして「王城一の強弓精兵(ゆよゆみせいびやう)」(嗣信最期)と謳われた能登守教経が、ここ下津井に在陣していた。
平家が都落ちしてから、機を見るに敏な阿波讃岐勢が源氏方につこうと動き始めていた。「そもそも、このあいだまで平家についとったんだから、いま源氏のもとへ参上しても信用されんだろう。さあさあ、平家に矢の一つでも射掛けて、それを証拠にして参ろうぞ。」
この動きを知った教経は「にっくき奴どもが。昨日今日まで我らの馬の草を切っていた者が、すでに心変わりしているとは。向こうがそのつもりなら、一人残らず討て。」そこまで戦うつもりのなかった阿波讃岐勢は、とてもかなわないと、戦わずして逃げ去ったということだ。
この下津井合戦と平行盛歌碑は直接関係があるわけではなさそうだ。行盛は清盛の孫。父の基盛は若くして亡くなった。以前の記事「日本初!馬の渡海作戦(藤戸・中)」で言及したように、その後の藤戸合戦では大将を務めた武将である。
合戦前夜という時期に行盛が交わした歌が、『玉葉和歌集』巻第十七「雑歌四」に掲載されている。
元暦元年世中さはかしく侍ける比平行盛備前の道をかたむとてたんの浦と申所に侍けるに八月十五夜月くまなきに過にし年は経正忠度朝臣なともろともに侍けるをいかはかり哀なるらんと思ひやられてそのよし申つかはすとて 全性法師
ひとりのみ波間にやとる月をみてむかしの友や面かけにたつ
返し 平行盛
もろともにみし世の人は波の上に面影うかぶ月そかなしき
全性法師は伝未詳だが、平家に近しい歌人だったようだ。寿永三年改め元暦元年(1184)、一ノ谷合戦で平家の主要武将が討たれ、世の中は騒然としていた。屋島を本拠地としていた平家勢は備前方面に進出しようとし、行盛は「たんの浦」に駐在していた。8月15日の満月、一ノ谷に散った経正や忠度とともに過ごした昔が思い出される。行盛の心中いかばかりかと全性法師が詠んだ。「波間の月を眺めていると、昔の友が思い出されることでしょう。」これに行盛は「おっしゃるとおり、昔が思い出されて哀しくなります。」と返した。
行盛のいた「たんの浦」とはどこなのか。下関の「壇ノ浦」でないことは確かで、似た地名は他に屋島の「檀ノ浦」がある。副碑の解説では下津井の「田之浦」だとする。行盛は屋島から備前をうかがっていたのかもしれないし、備前下津井に橋頭堡を築いていたのかもしれない。
全性法師は京から遠く離れた行盛の心中を思いやって詠んだのかもしれないし、行盛と同じ風景を見ていたのかもしれない。贈答歌の舞台は解釈の余地がありそうだが、行盛の哀傷は現代の私達の心にもよく響く。藤戸、屋島、そして壇ノ浦へと戦いは続き、あの教経も行盛も海に散ったことを思えば、世の無常がしみじみと感じられるのである。