朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、
「あ」
と幽(かす)かな叫び声をお挙げになった。
「髪の毛?」
スウプに何か、イヤなものでも入っていたのかしら、と思った。
「いいえ」
お母さまは、何事も無かったように、またひらりと一さじ、スウプをお口に流し込み、すましてお顔を横に向け、お勝手の窓の、満開の山桜に視線を送り、そうしてお顔を横に向けたまま、またひらりと一さじ、スウプを小さなお唇のあいだに滑り込ませた。
映画のワンシーンのような冒頭は『斜陽』というタイトルとともに、ノスタルジックなイメージで私の心を捉えた。だが、私の中の太宰治はこの程度で他にはほとんど読んだことがなかった。
三鷹市下連雀四丁目の禅林寺に「太宰治墓」がある。この日は6月19日。さすがに名にし負う桜桃忌である。多くの太宰ファンが訪れていた。太宰は本当のサクランボも好物だったのだろうか。
この日、太宰の弟子だった小野才八郎氏が「雀こ」と「海」を朗読してくださった。当時子どもの小さかった私は、父と子どもとのやりとりを描く「海」がとても印象に残り、その後新潮文庫で買い求め、しばらく通勤車中の愛読書としていた。場面は津軽に向かう五能線の車内である。
「海は、海の見えるのは、どちら側です。」
私はまず車掌に尋ねる。この線は海岸のすぐ近くを通っているのである。私たちは、海の見える側に坐った。
「海が見えるよ。もうすぐ見えるよ。浦島太郎さんの海が見えるよ。」
私ひとり、何かと騒いでいる。
「ほら! 海だ。ごらん、海だよ、ああ、海だ。ね、大きいだろう、ね、海だよ。」
とうとうこの子にも、海を見せてやる事が出来たのである。
「川だわねえ、お母さん。」と子供は平気である。
「川?」私は愕然(がくぜん)とした。
「ああ、川。」妻は半分眠りながら答える。
「川じゃないよ。海だよ。てんで、まるで、違うじゃないか! 川だなんて、ひどいじゃないか。」
実につまらない思いで、私ひとり、黄昏(たそがれ)の海を眺める。
「海」は短編集『もの思う葦』に所収されているが、その中に「一つの約束」という小品がある。
難破して、わが身は怒濤(どとう)に巻き込まれ、海岸にたたきつけられ、必死にしがみついた所は、燈台の窓縁(まどべり)である。やれ、嬉(うれ)しや、たすけを求めて叫ぼうとして、窓の内を見ると、今しも燈台守の夫婦とその幼き女児とが、つつましくも仕合せな夕食の最中である。ああ、いけねえ、と思った。おれの凄惨(せいさん)な一声で、この団欒(だんらん)が滅茶々々になるのだ、と思ったら喉(のど)まで出かかった「助けて!」の声がほんの一瞬戸惑った。ほんの一瞬である。たちまち、ざぶりと大波が押し寄せ、その内気な遭難者のからだを一呑(の)みにして、沖遠く拉(らっ)し去った。
もはや、たすかる道理は無い。
この遭難者の美しい行為を、一体、誰が見ていたのだろう。誰も見てやしない。燈台守は何も知らずに一家団欒の食事を続けていたに違いないし、遭難者は怒濤にもまれて(或いは吹雪の夜であったかも知れぬ)ひとりで死んでいったのだ。月も星も、それを見ていなかった。
そうなのだ。この世には私の知らないところに美しい行為がもっともっとあるのだと思う。日本中が泣いた!という感動大作もいいが、一隅を照らせば何気ない幸せが周りの人のおかげであることに気付くのかもしれない。

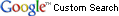
コメント