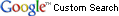来年春、皇太子殿下が譲位によって第126代天皇となられる。皇位が安定的に継承していくことは、誠に喜ばしいかぎりだ。だが歴史をたどれば、泥沼のような皇位継承もある。本日は、第97代天皇に数えられるはずであった悲劇の皇太子と、その異母兄で武士のように悲壮な死を遂げた皇子の物語をしよう。

敦賀市泉に「金崎城址碑」がある。隣には「金碕古戦場」という標柱もある。ここは「金ヶ崎城跡」という国指定史跡である。
建碑は明治11年8月12日、撰文は滋賀県令の籠手田(こてだ)安定、篆額は敦賀県知事を務めたことのある熊谷武五郎(直光)である。明治11年当時、この地域は滋賀県の一部だった。まずは、碑文を観察しよう。

「皇太子恒良及親王尊良」と恒良親王と尊良親王の名が確認できる。事の起こりはこうだ。建武三年(1336)初め、後醍醐天皇に反抗する足利尊氏は入京を果たしたものの、ほどなくして天皇方の攻勢により京を追われ九州に敗走する。
九州で尊氏を支援したのが宗像大社の宗像氏範である。力を得た尊氏は京に向かって攻め上り、5月25日の湊川決戦に勝利する。27日に天皇は比叡山に逃れ、6月14日に尊氏は京に入る。8月15日には、光厳上皇の院宣により光明天皇を即位させ、政治体制を整えていく。
尊氏は、比叡山の天皇方に和議を申し入れ、京へ戻るよう迫る。天皇は10月10日に京に戻ったが、その前日までに、密かに反転攻勢ができるよう手を打っていたのである。天皇は次のように新田義貞に言った。『太平記』巻第十七「立儲君被著于義貞事附鬼切被進日吉事」より
気比社の神官等敦賀津に城を拵(こしら)へて、御方(みかた)を仕由(つかまつるよし)聞ゆれば、先(まづ)彼(かしこ)へ下て、且(しばら)く兵の機を助け、北国を打随(うちしたが)へ、重(かさね)て大軍を起して、天下の藩屏となるべし。但(たゞし)朕京都へ出なば、義貞却(かへつ)て朝敵の名を得つと覚(おぼゆ)る間、春宮(とうぐう)に天子の位を譲て、同(おなじく)北国へ下し奉(たてまつる)べし。天下の事小大となく、義貞が成敗として、朕に不替(かはらず)此君(このきみ)を取立(とりたて)進(まゐら)すべし。
気比神宮の神官らが、敦賀に城を築き味方をすると聞いた。まず、そこへ向かい、しばらく軍備を整え、北陸諸国をしたがえて、再び大軍を編制し天下を守れ。ただ私が京へ戻れば、逆に義貞そなたが朝敵とされることだろう。そこで皇太子の恒良親王に譲位し、そなたと共に北陸に向かわせよう。天下のことは何でも義貞が判断し、私に対するのと同じく、新天皇を引き立ててやってくれ。
九日は事騒がしき受禅(じゅぜん)の儀、還幸の粧(よそほひ)に日暮ぬ。
受禅とは禅譲、天子の位を譲ることである。つまり10月9日に、後醍醐天皇は恒良親王に譲位した、と『太平記』に記されている。にもかかわらず恒良親王が歴代天皇に数えられないのは、後に京から吉野に脱出し南朝を樹立した後醍醐天皇が、譲位をなかったことにしたからである。
いっぽう新田義貞と子の義顕は10月13日、新天皇とされた恒良親王とその異母兄の尊良親王を奉じて、金ヶ崎城へ入った。この時、義貞らを支援したのが気比神宮の気比氏治である。尊氏と宗像大社との関係を思い起こさせる。

敦賀市曙町の氣比神宮境内に「旗掲松(はたかけのまつ)」がある。大きく育っているのは二代目で、旧松根が左側に残っている。
後醍醐天皇に味方した宮司、気比氏治が気比大明神の神旗を掲げたという松である。二人の親王と新田父子、そして氏治ら天皇方が金ヶ崎城にこもるや、すぐさま越前守護の斯波高経らの武家方は城を囲み、兵糧攻めに持ち込んだ。天皇方は新田義貞、脇屋義助の兄弟が城外に脱出し、攻囲する武家方を崩そうとしたが、多勢に無勢でどうにもならなかった。

敦賀市金ヶ崎町に「尊良親王御陵墓見込地」と刻まれた石柱がある。裏面には「明治九年十月」と建立時期が示されている。青色の美しい笏谷石である。
尊良親王の正式な陵墓は、京都市左京区南禅寺下河原町にあるので、敦賀の見込地は「自刃の地」と解されているようだ。親王はこの地でどのような最期を遂げたのであろうか。『太平記』巻第十八「金崎城落事」を読んでみよう。
新田越後守義顕は、一宮の御前に参て、合戦の様(やう)今は是までと覚え候。我等無力(ちからなく)弓箭(きうせん)の名を惜む家にて候間、自害仕らんずるにて候。上様の御事は、縦(たとひ)敵の中へ御出候共、失ひ進(まゐら)するまでの事はよも候はじ、唯(ただ)加様(かやう)にて御座有べしとこそ存候へと被申(まうされ)ければ、一宮何(いつ)よりも御快気(おんこゝろよげ)に打笑(うちえま)せ給て、主上帝都へ還幸成し時、以我(われをもって)元首将(ぐわんしゆのしやう)とし、以汝(なんじをもって)令為股肱臣(ここうのしんたらしむ)。夫(それ)無股肱(ここうなくして)元首持事(ぐわんしゆたもつこと)を得んや。されば吾命を白刃の上に縮めて、怨(うらみ)を黄泉(くわうせん)の下に酬(むく)いんと思也。抑(そも/\)自害をば、如何様(いかやう)にしたるがよき物ぞと被仰(おほせられ)ければ、義顕感涙を押へて、加様(かやう)に仕る者にて候と申(まうし)もはてず、刀を抜て逆手に取直し、左の脇に突立て、右の脇のあばら骨二三枚懸(かけ)て掻破(かきやぶ)り、其刀を抜て、宮の御前に差置(さしおき)て、うつぶしに成て死にける。一宮軈(やが)て其刀を被召(めされ)御覧ずるに、柄口(つかぐち)に血余(ちあまり)すべりければ、御衣(ぎよい)の袖にて刀の柄をきりきりと押巻(おしまか)せ給て、如雪(ゆきのごとく)なる御膚(おんはだへ)を顕(あらは)し、御心(おんむね)の辺(あたり)に突立(つきたて)、義顕が枕の上に伏させ給ふ。頭大夫行房、里見大炊助時義、武田与一、気比弥三郎大夫氏治、太田帥法眼以下御前に候(さぶらひ)けるが、いざさらば宮の御供仕らんとて、同音に念仏唱(となへ)て、一度に皆腹を切る。
新田義顕は、尊良親王のもとに来てこう申し上げた。
「合戦のようすを見ますと、もはやこれまでかと存じます。武運はつたないものでしたが、我らは武士にございますので、自害させていただきます。上様におかれては、たとえ敵に捕らわれても、お命まで失うことはございますまい。ただ、このような状況であることをご理解ください」
尊良親王は、いつもよりご機嫌に笑い、こう返した。
「後醍醐帝が都にお戻りになったとき、私を将軍とし、おまえを股肱の臣とした。臣がいなくて将軍が続けられるはずがなかろう。私も命を絶って、恨みをあの世で晴らすこととしよう。そもそも自害とはどうすればよいのじゃ?」
義顕は涙をこらえながら「こうするのでござい…」と言い終わらないうちに、刀を抜いて逆手に持ち、左の脇から右のあばら骨二三本にかけて切り、抜いた刀を親王の前に置いて、うつぶせに死んだ。
それに続いて親王は、置かれた刀を手にされたものの、柄が血まみれですべるので、着物の袖で刀の柄をきりきりと巻き、雪のように白い肌をあらわし、左胸に刀を突き立てて、義顕の上にお倒れになった。藤原行房、里見時義、武田与一、気比氏治、赤松帥法眼以下、親王にお仕えした者は「いざ、さらば。上様のお供つかまつらん」と、一斉に念仏を唱えて腹を切った。
尊良親王は後醍醐天皇の第一皇子とも第二皇子ともいい、歌をよくし将来を嘱望された時期もあったと伝えられる。新天皇とされた恒良親王は、一足先に小船で脱出を図ったが、武家方に捕らわれてしまい翌年亡くなった。今はのどかな金ヶ崎公園で、まさに滅びの美学の世界が繰り広げられたわけだ。
水戸藩の『大日本史』以来、敗戦に至るまで、南朝を正統とする歴史観が幅を利かせた。南北朝の正閏を論ずること自体が無意味だと思うが、南朝とこれを支えた人々に同情する気持ちはよく分かる。おそらく臨場感あふれる『太平記』の筆致のなせる業だろう。