『忠臣蔵』は吉良上野介と浅野内匠頭の対立から始まるが、物語の上では『太平記』が描いた高師直と塩冶判官の争いという設定である。「高」は高家の吉良であることを暗示し、「塩」は赤穂の塩、つまり浅野内匠頭を連想させる。吉良と浅野の対立の原因は諸説あるが、高と塩冶の対立は横恋慕に発している。
本日は塩冶判官の悲劇の舞台を訪ねたのでレポートする。こんな目に遭ったら、さぞかし悔しかろう。今回の取材で、復讐せずにはいられなかった赤穂四十七士の気持ちが分かる気がした。
姫路市豊富町豊富に「焚堂(やけどう)」がある。
木々の緑が美しいお庭に見えるものの、「焚堂」という名称がいわくありげに感じる。碑文を読むことにしよう。
太平記に暦応四年(一三四一)塩谷高貞の妻早田夫人(顔世御前)が尊氏の執事高師直の横恋慕により逆心ありと讒言され、出雲に逃れる途中、蔭山の宿で追手に攻められ、主従は草堂に火を放ち悲壮な最期を遂げたと記されている。
焚堂はその跡で石囲いは焼失した草堂と主従の灰塚、碑は文政二年(一八一九)村田継儒の撰により、圓通寺釈仙龍・安水政常などによって建立されている。
圓通寺縁起は菩提を祀るため焼け跡から出た持仏十一面観音を本尊とし、水月院圓通妙応大姉にちなんで圓通寺と号したとされている。
仮名手本忠臣蔵は、赤穂義士事件の内匠頭を塩冶判官に、吉良を師直に置きかえたものである。
尚、当時の日記「師守記」に高貞は蔭山で自害したと記されている。
ここでは簡潔に記されているが、『太平記』巻第二十一「塩冶判官讒死事」には、「悲壮な最期」が次のように描かれている。
八幡六郎は、判官が次男の三歳に成が、母に抱き附たるを抱て、あたりなる辻堂に、修行者の有けるに、「此少人、汝が弟子にして、出雲へ下し進せて、御命を助進せよ。必ず所領一所の主になすべし。」と云て、小袖一重副てぞとらせける。修行者かい/゛\しく請取て、「子細候はじ。」と申ければ、八幡六郎無限悦て、元の小家に立帰り、「我は矢種の有ん程は、防矢射んずるぞ。御辺達は内へ参て、女性少人を刺殺し進せて、家に火を懸て腹を切れ。」と申ければ、塩冶が一族に、山城守宗村と申ける者内へ走入り、持たる太刀を取直して、雪よりも清く花よりも妙なる女房の、胸の下をつきさくに、紅の血を淋き、つと突とほせば、あつと云声幽に聞えて、薄衣の下に伏給ふ。五つになる少人、太刀の影に驚て、わつと泣て、「母御なう。」とて、空き人に取附たるを、山城守心強かき抱き、太刀の柄を垣にあて、諸共に鐔本迄貫れて、抱附てぞ死にける。自余の輩二十二人、「今は心安し。」と悦て、髪を乱し大袒に成て、敵近附ば走懸々々、火を散してぞ切合たる。とても遁まじき命也。さのみ罪を造ては何かせんとは思ながら、爰にて敵を暫も支たらば、判官少も落延る事もやと、「塩冶爰にあり、高貞此にあり。首取て師直に見せぬか。」と、名乗懸々々々、二時許ぞ戦たる。今は矢種も射尽しぬ。切創負はぬ者も無りければ、家の戸口に火を懸て、猛火の中に走り入、二十二人の者共は、思々に腹切て、焼こがれてぞ失にける。
塩冶判官の次男で3歳になる子が母さんに抱きついていた。家来の八幡六郎がこれを抱き取って、近くの辻堂の修行僧に
「この子を貴殿の弟子として出雲へ連れて行き命を助け、どこかの領主にしてやってくれ」
と小袖を添えて渡した。修行僧は丁寧に受け取って
「ご心配には及びません。」
と答えた。八幡六郎は満足して元の小屋に戻り、
「矢のあるうちは私が防いでいよう。あなたがたは中へ入って母と子どもを刺し殺し、家に火を放って腹を切れ。」
と言うと、塩冶一族の山城守宗村が中に走り込み、手にする太刀を持ち直し、雪よりも清く花よりも美しい奥方の胸の下を刺すと鮮血が流れ、一気に突き通すと「あっ」という声がかすかに聞こえて、薄衣とともに倒れたのである。5歳になる長男が太刀を見てびっくりし、「わっ」と泣いて
「お母さーん」
と母に取りつくのを、山城守は心を鬼にして抱き取った。そして、太刀のつかを柱にあて、子どもとともに自らの体をつばまで刺し通し、抱きながら死んでいった。残る家来22人は
「もう心配することはない。」
と喜び、ざんばら髪に裸となり、近付く敵に向かって走りながら火花を散らしながら切り合った。助かる見込みのない命である。罪深いことをしてるのだから当然だと思いながら、ここでしばらく敵をとどめておけば、判官殿が少しでも遠くへ逃げられると思い、
「塩冶高貞、ここにあり。首を取って師直に見せるがよい。」
と名乗りながら、しばらく持ちこたえた。やがて矢が尽きたが、傷を負っている者もいないので、家の戸口に火を放って猛火の中へ走りこみ、22人の家来は思い思いに腹を切って焼け死んでいった。
凄惨な、あまりに凄惨な状況に言葉を失う。命とは何かという概念が、中世という時代や武士という立場で、現代の私たちとは異なっているようだ。塩冶判官の奥方も覚悟は決めていたであろうが、さぞかし無念であったろう。3歳の次男を修行僧に託すことができたのが、せめてもの救いだったかもしれない。
焚堂の敷地内に「陰山焚堂早田妙応夫人之碑」がある。地元の有志の発起により、文政二年(1819)に建てられた。「早田妙応夫人」は塩冶判官の奥方のことである。
この女性が顕彰されるのは単に気の毒だったからとか、顔世御前として『忠臣蔵』で演劇デビューしたからではない。高貴な生まれに加えて当代随一の美貌の持ち主で、後醍醐天皇ゆかりの女性だったのである。碑文には、次のように記されている。
夫人早田宮真覚女也生有殊色
後醍醐帝時以永嘉門院故入弘徽西台
帝之還幸伯耆也出雲人塩冶高貞率其属千余人赴之又前駆 乗輿入京師
帝嘉之妻以夫人
夫人は早田宮真覚(鎌倉将軍宗尊親王の子)の娘で、生まれながらに美貌であった。後醍醐天皇の時、永嘉門院(同じく宗尊親王の子)の縁で弘徽殿に入り西の台と呼ばれた。天皇が隠岐を脱出し伯耆へ戻られるや、出雲の塩冶高貞は配下の者千人余りを率いて駆け付け、京へ入る天皇の先導を務めた。天皇はこれをお喜びになり、高貞に夫人を妻として与えた。
これほどのお方に高師直ごときが横恋慕して、望みどおりになるわけがない。逆ギレした師直が高貞に逆心ありと讒言して、本日紹介している事態に至るわけだ。私は焚堂から帰ろうとして、ゆかりの場所をもう一つ見つけた。
焚堂の南に「袖かけの松」がある。落雷や松根油採取により戦後に枯れたらしく、株だけが丁寧に保存されている。
袖掛松とか腰掛石は貴人伝説の定番だ。酒井自治会による説明板には、次のように記されている。追討事件の概要を説明した後に続く一節である。
その折、村の入り口にひときわ目立つ松の木があり、その松に向かって夫人は夫の無事帰国を願いつつ、「松よ心あらば我が哀れな最期を無念の思いを後世に永く伝えよ」と自分の小袖を松の枝に掛けて祈られた。
哀れな最期と無念の思いは確かに伝わった。夫の塩冶判官は無事に出雲に帰国できたのだろうか。先ほど紹介した『太平記』巻第二十一「塩冶判官讒死事」の続きを読むと、
三月晦日(つごもり)に塩冶出雲国下着しぬれば…
とあるから帰国できたようだが、妻子が播磨の陰山で討たれたことを聞き、何度生まれ変わろうが師直に復讐することを誓って、
馬の上にて腹を切りさかさまに落ちて死にけり。
という最期だった。悔しい思いを抱きながら最期を迎えた地は松江市宍道町だと伝えられている。これはまたの機会にレポートしようと思う。
姫路市豊富町豊富と豊富町御蔭の境のあたりに「歯神さん」が祀られている。
その由来が姫路市教育委員会と酒井自治会それぞれの石碑で丁寧に語られている。追討事件の説明は省き、「歯」との関連部分だけ紹介しよう。
五輪塔残欠はこの付近で戦死した遺骸を供養するために建立されたと伝え、のち災厄から村を守る道祖神とみなされ、供養した村人の歯痛が治ったという伝承から歯神さんと呼ばれている。(姫路市教育委員会)
遺骨には、歯の部分が多く見受けられた。そのことに関連してか、村人で歯の病で苦しんでいた人がお参りすると治ったという。(酒井自治会)
「歯神さん」は戦死者の遺骸を供養した塔で、遺骨に歯が多かったから、歯痛を治す御利益があるとの信仰が生まれたという。歯痛除け信仰については、本ブログ記事「歯痛に効く観音様」や「歯神様となった南朝忠臣」、「皆立すくみにぞ死たりける」で紹介している。
そこで紹介した和田賢秀(にぎたけんしゅう)と頓宮又次郎(はやみまたじろう)は、どちらも南北朝の争いで活躍した武士である。同様に考えると姫路の「歯神さん」も、非命に倒れた塩冶側の人々が「歯噛み」して悔しがったことに由来すると思われるがどうだろうか。
最後に気になることを一つ。焚堂について説明した碑文に「尚、当時の日記「師守記」に高貞は蔭山で自害したと記されている。」とあることだ。「師守記」は北朝の公家、中原師守(もろもり)の日記で、史料としての信憑性が高い。実際の記述を確かめてみよう。続群書類従完成会『師守記』第一暦応四年三月二十九日条より
今日聞、隠岐大夫高貞於影山自害云々
『太平記』巻第二十一「塩冶判官讒死事」には、「播磨の陰山にては早追附れにけり。」とあり、表記はさまざまだが、いずれも播磨の蔭山荘を指している。高貞が出雲に帰国したとする『太平記』は物語としては面白いが、信憑性としては「師守記」に劣る。真相はどうなのか。
ヒントになるのは、顔世御前こと塩谷高貞の妻早田夫人である。生まれが南朝だけに、高貞も南朝関係者と接することが多かっただろう。讒言で陥れられたのではなく、火のない所に煙は立たぬと言われるように、北朝の高貞に何らかの動きがあった可能性は否定できない。
これに気付いた高師直がすばやく高貞を討伐したのだが、『太平記』の作者がストーリーを盛り上げるために脚色して、師直はより狡猾に、高貞と奥方はより悲哀に描いたのではなかろうか。
ただ、歴史は史実の追究のみを目的としていない。物語を楽しむことも大切だ。楽しくなければ歴史じゃないのだ。人は見たいもの聞きたいものを歴史に求めている。播磨で自害した高貞が、「塩冶判官讒死事」で出雲まで落ちのび、「仮名手本忠臣蔵」で浅野内匠頭の心情を仮託されたのも、そういうことだろう。史実はいつの間にか独り歩きを始めるのである。

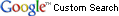
コメント